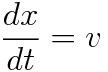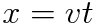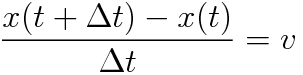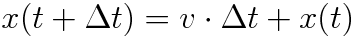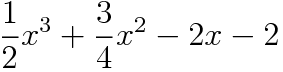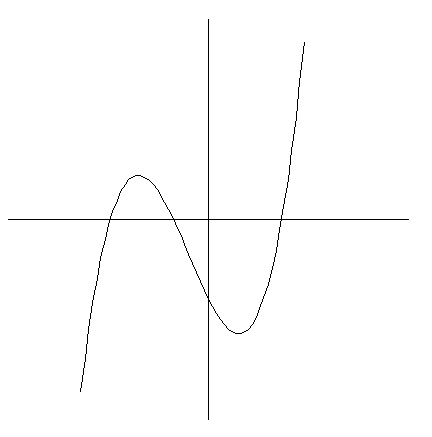学校の課題の休憩中にWinAPIの練習がてらいつものオセロを作ってみました。
Drawing関数はInvalidateRect()とかでWM_PAINT内で処理させた方がよかったかな。
最初に何よりも迷ったのがVisualC++でのWinプロジェクトの作成。
コンソールだとウィンドウとか出せないので、Winプロジェクトを作る必要があるんだけれど、
わざわざそんな初歩的なこと書いてないし、
なにより参考HPが基本的に以前のVerのVisualStudioだったりとか。
新規プロジェクト→Win32→Win32プロジェクトから作れます。
コンソールアプリケーションじゃだめ。
中身自体は空のプロジェクトでOK。そのあといつものように.cppを追加しとけば大丈夫。
とりあえずAPIの基本的な動き方はわかった(つもり)ので、
これからチェスとか作れればいいなぁなんて。
ちょっと前にもあったけどネタ。
http://www.gizmodo.jp/2011/06/667.html
これに対応する予定は今のところありません(笑)
以下リスト。
#include<windows.h>
#include <tchar.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
//const
#define WINDOW_WIDTH (430)
#define WINDOW_HEIGHT (340)
//grobal
RECT g_windowPos;
int board[10][10] = {0};
int buf_board[10][10] = {0};
int rev_board[10][10] = {0};
static int act = 1,wait = 2;//1 = player1,2 = player2
int rev_act = 2,rev_wait = 1;
//Prototype
HWND Create(HINSTANCE hInst);
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wp,LPARAM lp);
void OthelloInit(HWND hWnd);
void Drawing(HWND hWnd);
int Algo(int x,int y,HWND hWnd);
void Check(int x,int y,int i,int j,int *flag);
void REV(int flag,HWND hWnd);
int NUMSTONE(int color);
//Start
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst,
HINSTANCE hPrevInst,
LPSTR lpCmdLine,
int showCmd)
{
HWND hWnd;
MSG msg;
//Create Window
hWnd = Create(hInst);
if ( hWnd == NULL){
MessageBox(NULL,_T("Creating Window is failed"),_T("ERROR"),MB_OK);
return 1;
}
//Show Window
ShowWindow( hWnd, SW_SHOW);
UpdateWindow(hWnd);
OthelloInit(hWnd);
//Message Loop
while( 1 ){
BOOL ret = GetMessage( &msg,NULL,0,0);//Get Message
if( ret == 0 || ret == -1){
//if get Message of Shutdown,
//or failed GetMessage() (return -1),EndLoop
break;
} else {
//Message
TranslateMessage( &msg );
DispatchMessage( &msg );
}
}
return 0;
}
HWND Create(HINSTANCE hInst){
WNDCLASSEX wc;
// Window Class
wc.cbSize = sizeof(wc); //const size
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; //style
wc.lpfnWndProc = WndProc; //window procedure
wc.cbClsExtra = 0; //Extra Info1
wc.cbWndExtra = 0; //Extra Info2
wc.hInstance = hInst; //Instance handle
wc.hIcon = (HICON)LoadImage( //Icon
NULL,MAKEINTRESOURCE(IDI_APPLICATION),IMAGE_ICON,
0,0,LR_DEFAULTSIZE | LR_SHARED
);
wc.hIconSm = wc.hIcon; //child Icon
wc.hCursor = (HCURSOR)LoadImage( //Mouse Cursor
NULL,MAKEINTRESOURCE(IDC_ARROW),IMAGE_CURSOR,
0,0,LR_DEFAULTSIZE | LR_SHARED
);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);//Window Background
wc.lpszMenuName = NULL; //Menu Name
wc.lpszClassName = _T("Default Class Name");//Window Class Name
//Submit Window Class
if ( RegisterClassEx( &wc ) == 0){
return NULL;
}
//Window's location
g_windowPos.left = (GetSystemMetrics( SM_CXSCREEN ) - WINDOW_WIDTH )/2;
g_windowPos.top = (GetSystemMetrics( SM_CYSCREEN ) - WINDOW_HEIGHT )/2;
g_windowPos.right = g_windowPos.left + WINDOW_WIDTH;
g_windowPos.bottom = g_windowPos.top + WINDOW_HEIGHT;
//Create Window
return CreateWindow(
wc.lpszClassName, //Window Class Name
_T("Sample Program"), //Title bar
WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_THICKFRAME, //Window type
g_windowPos.left, //X
g_windowPos.top, //Y
WINDOW_WIDTH, //Window Width
WINDOW_HEIGHT, //Window Height
NULL, //Parent Window handle
NULL, //Menu Handle
hInst, //Instance Handle
NULL //Extra Data
);
}
//Window Procedure
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wp,LPARAM lp)
{
static int x,y;
static BOOL draw = FALSE;
HWND hButtonWnd;
HINSTANCE hInst;
hInst = (HINSTANCE)GetWindowLong(hWnd,GWL_HINSTANCE);
switch( msg ){
case WM_LBUTTONUP:
x = LOWORD(lp);
y = HIWORD(lp);
if(x >= 20 && x <= 55+34*7 && y >= 20 && y <= 55+34*7){
Algo(x,y,hWnd);
Drawing(hWnd);
}
return 0;
case WM_RBUTTONUP:
if(act == 1){
act = 2;
wait = 1;
}else if(act == 2){
act = 1;
wait = 2;
}
Drawing(hWnd);
return 0;
case WM_CREATE:
hButtonWnd = CreateWindow(
_T("BUTTON"),_T("UNDO"),
WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON,
310,20,100,30,hWnd,(HMENU)1000,hInst,NULL);
hButtonWnd = CreateWindow(
_T("BUTTON"),_T("RESTART"),
WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON,
310,260,100,30,hWnd,(HMENU)2000,hInst,NULL);
break;
case WM_COMMAND:
switch(LOWORD(wp)){
case 1000:
REV(2,hWnd);
Drawing(hWnd);
break;
case 2000:
OthelloInit(hWnd);
return 0;
}
break;
case WM_CLOSE:
if( MessageBox(hWnd,_T("shutdown?"),_T("checking"),MB_YESNO ) == IDNO){
return 0;
}
break;
case WM_DESTROY://when Window Destroy
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
//other Messages is DEFAULT
return DefWindowProc(hWnd,msg,wp,lp);
}
void OthelloInit(HWND hWnd){
int i,j;
act = 1;
wait = 2;
for (i = 0;i < 10;i++){
for(j = 0;j < 10;j++){
board[i][j] = 0;
}
}
for (i = 0;i <; 10;i++){
board[i][0] = 8;
board[i][9] = 8;
board[0][i] = 8;
board[9][i] = 8;
rev_board[i][0] = 8;
rev_board[i][9] = 8;
rev_board[0][i] = 8;
rev_board[9][i] = 8;
}
board[4][5] = 1;
board[5][4] = 1;
board[4][4] = 2;
board[5][5] = 2;
rev_board[4][5] = 1;
rev_board[5][4] = 1;
rev_board[4][4] = 2;
rev_board[5][5] = 2;
EnableWindow(GetDlgItem(hWnd,1000),FALSE);
Drawing(hWnd);
}
void Drawing(HWND hWnd){
int i,j;
char word[50];
RECT rc;
HDC hDC;
HBRUSH hBrush;
HPEN hPen;
WCHAR prev_word[50];
hDC = GetDC(hWnd);
/*
GetClientRect(hWnd,&rc);
InvalidateRect(hWnd,&rc,FALSE);
*/
hPen = CreatePen(PS_NULL,0,0);
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(255,255,255));
SelectObject(hDC,hPen);
SelectObject(hDC,hBrush);
Rectangle(hDC,310,160,400,200);
DeleteObject(hPen);
DeleteObject(hBrush);
//GetStockObject(BLACK_PEN);
SelectObject(hDC,(HPEN)GetStockObject(BLACK_PEN));
for (i = 0;i < 8;i++){
for (j = 0;j < 8;j++){
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0,255,0));
SelectObject(hDC,hBrush);
Rectangle(hDC,20+34*i,20+34*j,55+34*i,55+34*j);
DeleteObject(hBrush);
switch(board[i+1][j+1]){
case 1:
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));
SelectObject(hDC,hBrush);
Ellipse(hDC,22+34*i,22+34*j,53+34*i,53+34*j);
DeleteObject(hBrush);
break;
case 2:
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(255,255,255));
SelectObject(hDC,hBrush);
Ellipse(hDC,22+34*i,22+34*j,53+34*i,53+34*j);
DeleteObject(hBrush);
break;
}
}
}
SetRect(&rc,310,100,400,150);
switch(act){
case 1:
DrawText(hDC,_T("Black turn"),-1,&rc,0);
break;
case 2:
DrawText(hDC,_T("White turn"),-1,&rc,0);
break;
}
sprintf_s(word,30,"black = %d\nwhite = %d",NUMSTONE(1),NUMSTONE(2));
mbstowcs_s(0,prev_word,30,word,_TRUNCATE);
SetRect(&rc,310,160,400,200);
DrawText(hDC,prev_word,-1,&rc,DT_WORDBREAK);
ReleaseDC(hWnd,hDC);
}
int Algo(int x,int y,HWND hWnd){
int locx,locy,i,j,flag;
for(i = 0;i < 8;i++){
if (x >= 20+34*i && x <= 55+34*i){
locx = i+1;
}
if (y >= 20+34*i && y <= 55+34*i){
locy = i+1;
}
}
if(board[locx][locy] != 0){
return -1;
}
if(locx >= 1 && locx <= 8 && locy >= 1 && locy <= 8){
/*置き石判定*/
flag = 0;
REV(flag,hWnd);
for (i = -1;i <= 1;i++){
for(j = -1;j <= 1;j++){
Check(locx,locy,i,j,&flag);
}
}
if(flag != 0){
REV(flag,hWnd);
board[locx][locy] = act;
if(act == 2){
rev_act = act;
rev_wait = wait;
wait = act;
act = 1;
} else {
rev_act = act;
rev_wait = wait;
wait = act;
act = 2;
}
}
}
return 0;
}
void Check(int x,int y,int i,int j,int *flag){
int k,num;
if(board[x+i][y+j] == wait){
num = 0;
while(1){
if(board[x+i][y+j] == wait){
num++;
} else if (board[x+i][y+j] == act){
for(k = 0;k < num;k++){
board[x-i*k][y-j*k] = act;
}
*flag = 1;
break;
} else if(board[x+i][y+j] == 8 || board[x+i][y+j] == 0){
break;
}
x += i;
y += j;
}
}
}
void REV(int flag,HWND hWnd){
int i,j;
if(flag == 0){
for(i = 0;i < 10;i++){
for(j = 0;j &t; 10;j++){
buf_board[i][j] = board[i][j];
}
}
} else if(flag == 1){
for(i = 0;i < 10;i++){
for(j = 0;j < 10;j++){
rev_board[i][j] = buf_board[i][j];
}
}
EnableWindow(GetDlgItem(hWnd,1000),TRUE);
} else if(flag == 2){
act = rev_act;
wait = rev_wait;
for(i = 0;i < 10;i++){
for(j = 0;j < 10;j++){
board[i][j] = rev_board[i][j];
}
}
EnableWindow(GetDlgItem(hWnd,1000),FALSE);
}
}
int NUMSTONE(int color){
int i,j,num;
num = 0;
for(i = 0;i < 10;i++){
for(j = 0;j < 10;j++){
if(board[i][j] == color){
num++;
}
}
}
return num;
}